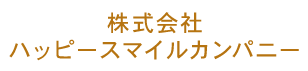1. 歯科衛生士 ミッキーの離乳食研究とは
こんにちは!歯科衛生士のミッキーです。
私は10年以上にわたって、赤ちゃんの「噛む力」を育むための離乳食研究を行っています。
このブログでは、ミッキーの離乳食研究として、 「一般的な離乳食」と「手づかみ離乳食」の違いについて、管理栄養士と共に研究を進め、一般的な離乳食から手づかみ離乳食へと移行をまとめたものです。
本日の研究テーマは「椅子に座らず立ってしまう」です。
2. こだわりと自我
1歳半ごろになると、子どもの行動に「こだわり」が強く出てきます。
お気に入りのコップじゃないと飲まない、靴を自分で履きたがる、片づけると泣いて怒る…。親からすると「なんでこんなに頑固なの?」と驚くこともあるでしょう。
でも実はこれ、「自分と他人の区別」が芽生えてきた証拠です。「これは自分の気持ち」「これは自分でやりたい」と、自我が芽生えてきた証拠であり、子ども自身のこだわりになります。
さらに、子どもは日々たくさんの刺激を受けており、その中には楽しいだけでなく、不安を感じることもあります。そんなときにお気に入りの物や、自分なりのやり方に固執するのは、「安心感を得るため」の行動でもあります。
Aちゃん(1歳5ヶ月)のこだわりは、自転車のヘルメットをかぶることです。家の中でもずっとかぶっているそうですが、この日は食事のときに自ら外しました。小さな変化ですが、「状況に合わせて行動を切り替えられる力」が育っていることを示しています。
つまり“こだわり期”はわがままではなく、自我が芽生え始めた自分の心を育てるための練習時期です。困った行動に見えても、成長の証だと認めて出来るだけ見守ってあげましょう。
3.本日の離乳食研究:椅子に座らず立ってしまう
今回のAちゃんが食事をする時にも、いくつかの発達したサインが見られました。
最初に味噌汁に手を入れ「あつっ!やだっ」と言い、しばらくするともう一度試して「やだっ」。
これは単なるいたずらではなく、「熱い」という感覚を確認し、さらに言葉で気持ちを伝えている行動です。危険を学ぶと同時に、言葉の使い方を覚えている大切なステップです。
大根の煮物は前歯でしっかりかじり取り、美味しそうに食べました。一方、肉団子は「やだっ」と拒否。食べたい・食べたくないを自分の言葉で伝えられるようになってきたことは、まさに自己主張の始まりです。

次に出したさつまいもは、最初は「べーっ」と吐き出しましたが、その後、皮を自分で器用にむきました。1歳5ヶ月でここまで細かい動きができるのは驚きです。これは「手づかみ食べ」を通して育まれた、細かい作業の力の成果といえるでしょう。

そして、食事中に椅子へ立ち上がる行動も見られました。保護者にとってはヒヤッとする場面ですが、これは子どもの「自由への欲求」を示す行動でもあります。
椅子のガードは安全のためにありますが、子どもにとっては動きが制限されてしまうこともあります。大切なのは「ガードは縛るためではなく守るため」という視点です。
成長の一つの目安として、背もたれのない椅子に安定して座れるようになれば、ガードを外すタイミングとも言えます。
窮屈そうなときはガードを少し緩めるのも一案です。それでも座らずに立ち上がるときは、無理に座らせず一度椅子から下ろし、床で食べるのも安全で現実的な方法です。

4. まとめ
今日のAちゃんの行動から見えた成長サインは…
- 「やだっ」と言葉で自分の意思を伝える力
- サツマイモの皮を自分でむく巧緻性の発達
- 椅子から立ち上がることで示した自由への欲求
これらはすべて健やかな成長の証です。
「食べなかった」「立ち上がった」といった行動に目が行きがちですが、実はその裏に「新しくできるようになったこと」がたくさん隠れているのです。
離乳食の時間は栄養をとる場であると同時に、心・体・社会性を育てる場でもあります。今日のような小さな一コマからも、大きな学びがあるのです。