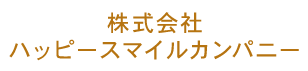1. 歯科衛生士 ミッキーの離乳食研究とは
こんにちは!歯科衛生士のミッキーです。 私は10年以上にわたって、赤ちゃんの「噛む力」を育むための離乳食研究を行っています。
このブログでは、ミッキーの離乳食研究として、「一般的な離乳食」と「手づかみ離乳食」の違いについて、管理栄養士と共に研究を進めたときのお話をしています。
本日の研究テーマは「離乳食スプーン介助から手づかみ離乳食移行へのその後」です。
Aちゃんは離乳食スプーン介助から手づかみ離乳食への移行をはじめ5ヶ月あまりが経ちました。手づかみ食べでの経験を積み、指先の使い方が上手になり、今までできなかったことができるようになりました。
2. 言葉の理解
Aちゃんは、私たちの「できたね」「上手だね」という言葉に反応し、ニコニコと笑顔で手を叩く様子が頻繁に見られました。これは先月までは見られなかった様子です。
私は言葉の専門家ではありませんが「1歳前後の言葉の理解」を調べてみると、赤ちゃんが大人の話す言葉を理解するようになるのは、1歳前後ということです。
「こんなことを話しても、まだわからないかな」と思わず、積極的に話しかけることが良いようです。
Aちゃんは1歳2ヶ月になりました。Aちゃんの家族は父・母・双子の兄(8歳)の5人家族です。手づかみ食べにも慣れてきて、家族揃って食事ができるようになりました。
食事の席は、Aちゃんの前に双子のお兄ちゃんが座っていて、Aちゃんが離乳食を食べるとお兄ちゃん2人が手を叩いて褒めてくれるそうです。
このお兄ちゃんの行動を、Aちゃんも見て真似するようになり先ほどの行動に繋がったのでしょう。
言葉と行動の理解が深まり、家族とのコミュニケーションが豊かになってきた証です。
私たちがAちゃんを褒めると、兄の言葉・行動を理解したAちゃんが、兄と同じ行動をするということも興味深いことでした。
3. 本日の離乳食研究:離乳食スプーン介助から手づかみ離乳食移行のその後
Aちゃんは先月に比べ、手・指の使い方が上手になり、先月できなかったことができるようになりました。
食育実践予防歯科®メソッドでは離乳食初期(1回食)から手づかみ食べを推奨していますが、Aちゃんは一般的な離乳食で生後6ヶ月からスプーン介助離乳食を始め、生後9か月後から手づかみ食べを始め、そこから徐々に手づかみ食べに移行しました。
離乳食初期(1回目)から手づかみ食べをしているお子さんに比べ、Aちゃんは手の発育がゆっくりでした。食育実践予防歯科®メソッドでは離乳食中期(2回食)の頃にできる汁椀でのすすり飲みも、先月観察した時には、汁椀をうまく傾けられずにこぼしてしまっていたのですが、今月はしっかり両手で持って、こぼさずに汁を飲めるようになりました。また今月は汁椀の中から具を取り手づかみ食べしていました。

先月はご飯茶碗からおかゆをつかみ食べることができませんでしたが、今月はお茶碗からおかゆを指先でとり上手に食べることもできました。
指先の動きを見ると、全部の指先を上手に使い、先月より細かい動きができるようになりました。
このことからも、手を使う手づかみ食べをしていると、手の発達が早くなり、赤ちゃんは経験を積めば積むほど上達するということがわかりました。

Aちゃんは食事に満足するとお皿を重ね、ご馳走様の合図です。
丸と丸を重ねるという知的な行動もできるようになりました。

4. まとめ
Aちゃんがスプーン介助の離乳食から手づかみ食べに移行してから、あっという間に5ヶ月が経ちました。最初はうまく指が使えず、思うように食べられなかったAちゃんですが、今では指先の動きの細やかさも明らかに上達し、驚くほど成長を見せてくれています。
こうした成長には、日々の積み重ねが大きく影響しているのでしょう。毎日の手づかみ食べが、自然と指先の発達や集中力を育てているのが伝わってきます。
食事の時間が、ただの栄養補給ではなく、心の発達や家族の絆を育む大切なひとときになっているのです。
Aちゃんの知的な成長も感じられるようになりました。しっかりお口を閉じて噛んで食べる姿には、「噛む子」がすくすく育っている手応えもあり、とても嬉しい気持ちになります。
毎日の小さな「できた!」の積み重ねが、赤ちゃんの口・心・体を豊かに育んでくれるんですね。