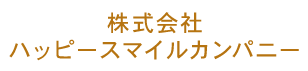1. 歯科衛生士 ミッキーの離乳食研究とは
こんにちは!歯科衛生士のミッキーです。
私は10年以上にわたって、赤ちゃんの「噛む力」を育むための離乳食研究を行っています。
このブログでは、ミッキーの離乳食研究として、 「一般的な離乳食」と「手づかみ離乳食」の違いについて、管理栄養士と共に研究を進めたときのお話をしています。
本日の研究テーマは「離乳食3回食(後期)の食材と進め方の違い」です。
離乳食3回食(後期)では一般的な離乳食と食育実践予防歯科®メソッドと大きな違いがあります。
食育実践予防歯科®メソッドでは1回食(初期)から手づかみ食べをはじめますが、一般的な離乳食では生後9ヶ月頃よりメニューの中の1品に手づかみの食材を入れていきます。
生後9ヶ月頃は一般的な離乳食では3回食(後期)にあたる時期なので人参スティック・大根スティックの実食をしました。
2. 一般的な離乳食と手づかみ離乳食の進め方の違い
赤ちゃんが栄養や食べる力を発達させ、徐々に普通の食事に移行する準備を整えることです。この時期には、食材の種類や食べ方を広げ、噛む力や食事への興味を育む時期です。
1)一般的な離乳食の進め方(3回食・後期)
一般的な離乳食の進め方では、「正しい栄養摂取」のバランスを大切にしながら、無理のないペースで進めるのがポイントです。一般的な離乳食は保護者のスプーン介助離乳食の中に1品手づかみの食材が入ります。
食材:今回の研究で使用の食材
- 分搗き米5分粥
- ひじきとポテトのサラダ
- じゃがいもと人参煮
- にんじんスティック・大根スティック※1
※1:手づかみする食材です。
家族の食事を作りながら離乳食を作るのは大変です。この時期になると食べられる食材がほぼ大人と同じになるため、大人の料理の味つけをする前に離乳食用に取りわける方法も活用できます。
主食のお粥は5分粥ですが、栄養のことも考えお米を白米にせずに栄養価の高い分搗き米※2でお粥を作ることもおすすめです。おかずは鍋で煮込みトロミをつけます。
一般的な離乳食ではまだ飲み込みがうまくできないので、このトロミが必要という考え方です。片栗粉のかわりにお粥をトロミの代用にし、おかずにお粥を混ぜるという方法もあります。
ただ、お粥におかずを混ぜる場合は、トロミをつけるだけにし、主食にならないようにしましょう。
日本には、口中調味(こうちゅうちょうみ)というご飯とおかずを交互に食べ、口の中でご飯におかずの味を重ねて味わう食文化があります。
ご飯におかずを混ぜるのでは、口中調味でなくなります。おかずにご飯を混ぜる目的は、あくまでもお粥をトロミの代用として飲み込みやすくするということです。
※2:分搗き米とは玄米の外皮(ぬか)を部分的に削減した状態のお米のことです。精米の度合いによって「〇分搗き」と表現され、玄米と白米の中の位置するお米です。
手づかみ食べが始まると自分でやりたいという気持ちが強くなり、介助で使っているスプーンを赤ちゃんが奪い取ろうとしたり、食べたいという食に対しての意欲が強くなり、スプーン介助の時に赤ちゃんが前のめりになり、保護者とタイミングが合わず、スプーン介助する事が難しいという事もでてきます。

2)手づかみ離乳食の進め方(3回食・後期)
食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食は月齢で進めることはしません。
離乳食初期・中期で手づかみ食べをしている子は前歯でかじり取り、取り込んだものを舌と上顎でつぶすことが出来ます。
初期・中期では、舌の動きが前後の動きから、上下に動くようになり、後期になると左右に動くようになります。お粥も野菜もタンパク質も全て手づかみで食べます。
3回食(後期)からは食材がかなり増えるため、栄養バランスが整いやすい一汁三菜の献立をめざしましょう。
一汁二菜とは日本人の主食である「ご飯」に、「汁物」と「主菜 副菜(おかず)」を組み合わせた献立です。栄養バランスよく献立を組むことができます。
主食は5倍粥で、つぶさずに与えます。
主菜はタンパク質となる食材で、例えば魚は白身魚以外にもマグロ・アジなどの魚に挑戦し、食べられる種類を増やしていきましょう。
魚は片栗粉をまぶして、だし汁で弱火でじっくり煮る+とろみあん(大根ソース・コーンソースなど)をかけます。
副菜は野菜の軟らかさは2回食(中期)と変わらずで良く、トロミは必要としませんが煮汁は必要です。煮汁がないとパサパサして食べにくく、口が開く傾向にあります。
大きさは野菜の大きさにより丸型または半月です。口の中に入れこまないように、口幅より大きいサイズが良いです。このサイズにすることで口の中に入れこまず、かじり取りをします。
味つけは混合だし+調味料(醤油・みりんを混ぜた)1〜2滴ほどで充分です。
3. 本日の離乳食研究:離乳食3回食(後期)の初めての手づかみ食べ
ここでは初めて手づかみ食べをしたAちゃんの様子と食育実践予防歯科®メソッド手づかみ離乳食3回食(後期)の手づかみ食べについて解説していきます。
Aちゃんは陶器のお皿に入ったにんじんスティックを渡されると、まずお皿に反応しました。
お皿を舐めたり、お皿でテーブルをたたいたりしました。この反応は食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食でも見られる光景で、2回食(中期)に見られます。
これはおもちゃと食器の区別ができていないという反応で、手や舌で「何かな?」と確かめている様子です。陶器では割れたりすると危ないので、この様子が見られる時はプラスチックのお皿をおすすめします。
初めての手づかみ食べでしたが、上手に口に入れていました。Aちゃんの笑顔は本当に嬉しそうでした。

しかし、にんじんスティックが硬かったようで「おぇ」とスムーズに飲み込めていない様子や、モグモグしている時に口が開いてしまう事もありました。
次に大根スティックを渡され、Aちゃんは眉間にしわを寄せました。
これは大根の苦みに反応したのだと思います。特に夏大根は苦みが強く、硬いので赤ちゃんによっては食べない赤ちゃんもいます。Aちゃんは眉間にしわを寄せたものの食べていました。
手づかみ食べをした後に、保護者がスプーン介助で離乳食を与えると、手をだそうとしたり、テーブルをトントンと叩いていました。これは赤ちゃん自身が「もっとやりたい」「もっと食べたい」の表現ではないでしょうか。
食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食では、目と手と口の高度な協調運動もできるようになり、力加減なども調整が出来ます。食器から取った食材を、また元の食器に戻すことが出来ます。
食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食は月齢で進めることはしませんが、3回食(後期)スタートはもう少し後の月齢となりますので、Aちゃんとの違いが出るのは当然のことです。
Aちゃんはにんじんスティックを渡されていましたが、見て選ぶということも目と手と口の協調運動には大事な要素なので、テーブルに、にんじんスティック、大根スティックを置き、Aちゃんが選び、手づかみをし、口に持っていく経験をすることが高度な協調運動を促しやすくなります。
4. まとめ
離乳食1回食(初期)、2回食(中期)が保護者のスプーン介助による離乳食だとしても、手づかみ食べできる体が整っていれば、途中から手づかみ食べはできるという検証結果でした。
手づかみ食べを始めるのが1歳過ぎのお宅が多いようですが、1歳過ぎから手づかみ食べを始めるのと、9ヶ月頃から手づかみ食べを始めるのでは、赤ちゃんの手づかみ食べの経験の時間が違います。時間の差は経験の差になります。
手づかみ食べは食に対しての意欲も高くなり、離乳食を通じた経験は赤ちゃんの口・心・からだの発育に良いです。
手づかみ食べができる体が整ったなら、早い時期から手づかみ食べにチャレンジしてほしいです。