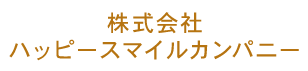1. 歯科衛生士 ミッキーの離乳食研究とは
こんにちは!歯科衛生士のミッキーです。
私は10年以上にわたって、赤ちゃんの「噛む力」を育むための離乳食研究を行っています。
このブログでは、ミッキーの離乳食研究として、 「一般的な離乳食」と「手づかみ離乳食」の違いについて、管理栄養士と共に研究を進めたときのお話をしています。
本日の研究テーマは「離乳食3回食(後期)の手づかみ食べ」です。
厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」によると、手づかみ食べは離乳食後期の9ヶ月頃から始まり3回食(後期)の9ヶ月~11ヶ月が手づかみ食べに適している時期との事です。
個人差はありますが、9ヶ月頃からさまざまな感触に興味を示し、手をのばすようになります。手づかみ食べの最初は柔らかく手に持ちやすく、手が汚れにくい食材から始め、歯茎で潰せるくらいの軟らかさで手づかみ食べができる食材を1品分用意するというのが一般的な離乳食指導のようです。
食育実践予防歯科®メソッドの3回食(後期)では、歯ぐきでつぶせる軟らかさとし、舌を左右にふって歯ぐきでつぶすことができます。大きな食材を自分自身で持ったり、親指、人差し指、中指の3指でつまむなど、指先のコントロールもできるようになり、手づかみで食べるということが自由自在にできるようになる時期です。
2. 一般的な離乳食と手づかみ離乳食の手づかみ食べの違い
この研究ブログは、一般的な離乳食の進め方と食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食の違いをテーマとしています。
1)一般的な離乳食の手づかみ食べ
離乳食後期は手づかみ食べ練習の時期です。一般的な離乳食では「持ちやすさ」が優先するようで食材として剥いたみかんやりんごといった果物、おやき、卵焼き、パンケーキ、パン、初期より少し大きめに切ったやわらかめの野菜などです。形状はスティック状や小判型が適しているとの事です。離乳食メニューの中の1~2品手づかみできるものがあれば良いです。
手づかみ食べを始める時期のサインとなる動作
- 食べ物をすぐ飲み込まず、時々左右に口が動く
- 食べ物をじっと見つめたり、手を伸ばしたりする
- おすわりが安定し、食事用の椅子などに一定の時間座っていられる
- 口どけのいいものを歯ぐきでかもうとする
手づかみ食べに移行できないサイン
- 口をあまり動かさず、食べ物をまる飲みしている
- 離乳中期(7~8カ月ごろ)のかたさや大きさの食べ物を口から出してしまう
2)食育実践予防歯科®メソッド離乳食の手づかみ食べ
食育実践予防歯科®メソッドでは1回食の前に準備期を設け、準備期ではサラサラ重湯・トロトロ重湯、10倍粥つぶし、にんじんペーストの順に保護者のスプーン介助により与えます。
1回食(初期)から3回食まで全て手づかみ食べとなります。
食育実践予防歯科®メソッド離乳食では、手づかみ食べを始める時期のサインは、【赤ちゃんが自座位できる体の状態】であるかどうかを指標にしています。
食育実践予防歯科®メソッド離乳食の1回食(初期)から3回食のご紹介
1回食(初期)
- 炭水化物
- 野菜
1回食(初期)では10倍粥、かなりやわらかく煮た人参スティック、大根スティックです。
2回食(中期
- 炭水化物
- 主菜(タンパク質)
- 副菜(野菜)
2回食(中期)では炭水化物は7倍粥で、つぶさずに与えます。
タンパク質について
タンパク質は豆腐(絹豆腐)を混合だし汁で沸騰させないように弱火で煮たものや、塩抜きしたしらすを使います。しらすに慣れたら白身魚(生鮭)に挑戦です。
白身魚は片栗粉をまぶして、混合だし汁で弱火でじっくり煮てとろみあんをかけます。白身魚(生鮭)に慣れたら、鶏ささみ肉に挑戦します。
鶏ささみ肉は筋をとってからフードプロセッサーにかけ、ミンチにして使います。鶏ささみひき肉だけだとかたいので、豆腐を混ぜてかたさを調整します。
野菜について
野菜は、にんじんと大根を丸型に切り、舌と顎で押しつぶせるやわらかさに煮たあとで、スティック状または半月状に切ります。ブロッコリー、ごぼうなどもメニューに加わります。
3回食(後期)
- 炭水化物
- 主菜(タンパク質)
- 副菜(野菜)
3回食(後期)では主食は5倍粥で、つぶさずに与えます。
タンパク質について
主菜はタンパク質となる食材で、例えば魚は白身魚以外にもマグロ・アジなどの魚に挑戦し、食べられる種類を増やしていきます。
\point!/
魚は片栗粉をまぶして、だし汁で弱火でじっくり煮る+とろみあん(大根ソース・コーンソースなど) をかけます。
副菜は野菜の軟らかさは2回食(中期)と同じ良く、トロミは要りません。 しかし煮汁は必要です。煮汁がないとパサパサして食べにくく、口が開く傾向にあります。
\point!/
大きさは野菜の大きさにより丸型または半月です。口の中に入れこまないように、口幅より大きいサイズが良いです。このサイズにすることで口の中に入れこまず、かじり取りをします。
3.本日の離乳食研究:離乳食3回食(後期)における手づかみ離乳食への移行
Aちゃんは生後10ヶ月、下の前歯が2本生えています。
一般的な離乳食における手づかみ食べ真っ只中の月齢で、離乳食は月齢基準での提供でした。
提供されたものは歯ぐきでつぶせるかたさの人参スティックと2cm角の大根でした。
Aちゃんは9ヶ月から始めた手づかみ食べが上手になっていましたが、人参も大根もべっーと吐き出していました。Aちゃんのような様子が見らえる時に保護者は、「嫌いなんだね」と言う方が多いですが、これはAちゃんの口はまだ歯ぐきでつぶせる機能が整っていないというサインです。
Aちゃんの舌の動きはまだ舌を上顎につけて押しつぶせることはできますが、左右に舌を動かし、歯ぐきでつぶすことは難しい状態だということです。
離乳食3回食(後期)手づかみ離乳食への移行も、食育実践予防歯科®メソッドの手づかみ離乳食と同じように、赤ちゃんが手づかみのステップを一つずつ経験していくことが必要のようです。

4.まとめ
食育実践予防歯科®メソッドでは手づかみ食べスタートは月齢でなく、赤ちゃんが「自座位できる」体であるということです。
現代において自座位ができる月齢をあえて示すなら平均8ヶ~9ヶ月くらいです。一般的な離乳食3回食(後期)の手づかみ食べは、9~11ヶ月が適期と言われていますので、食育実践予防歯科®メソッドと同じ時期に当たります。
離乳食スタートは保護者の介助で始めたとしても、赤ちゃんが自座位できるようになれば、保護者の介助から手づかみ離乳食に移行できます。
手づかみ食べは口や手の発達を促ながし、手づかみで食べることで、指先の器用さや手の発達を鍛えられ、脳の発達も刺激されます。
何よりも赤ちゃんの食べる意欲が育まれるのでぜひ積極的に取り組んでいただきたいです。